前回の記録から大分時間が経ちましたが、カナダ・バンクーバーにある「ダグラスカレッジ」の試験事情について記録します。
今回説明している試験は、すべて「オンライン」で実施されたものです。
- カナダの公立カレッジ進学に興味がある
- カレッジでIT分野を学びたい
- カナダの公立カレッジの試験事情(オンライン)を知りたい
といった方におすすめの記事です。
前回の記事はこちら↓
記事を書いている人
専攻はIT系です。ネットワークの基礎知識やプログラミングについて学んでいました。
ITの分野は未知の領域です。今回記事にした学期では、4科目受講していました。
試験の種類

学期中、以下3種類の試験がありました。
- Quiz(小テスト)
- Mid-term examination(中間試験)
- Final examination(期末試験)
いずれの場合でも、①Zoom等にログインし、②別ブラウザでWeb上の試験を受けるためのシステムにログインした上で、試験を受けます。
1学期間における試験実施のタイミング

夏学期は5月初旬~8月中旬までの約3.5か月間でした。
5月:小テスト(下旬)
6月:小テスト(時期は科目により異なる)、中間試験(中旬~下旬)
7月:小テスト(時期は科目により異なる )
8月:期末試験(初旬~中旬)
小テストについて
・時期 毎月1回程度(科目により実施時期は異なるが、どの科目も最低2回はあった)
・試験時間 20分~1時間
・出題範囲 1~3章※¹+Lab※²で学んだ内容
・出題形式 Multiple choice questions(MCQ)‐選択式‐ がメイン。プログラミングの授業は課題が1つ与えられ、実際にコードを書くスタイル。
※¹ 1章:教科書50ページ~70ページ分くらい
※² Lab:座学ではなく実際に手を動かして学ぶ実技形式の授業のこと
蛇足ですが、教授陣は当然のようにMCQ、MCQと連呼していたので、略称を覚えておくと混乱せずに済みます。
私は意味を知りませんでした。
小テストのあとは、時間が余るので普通に授業をやります。(通常授業時間は2~3時間ほど)
中間試験について
・時期 6月中旬~下旬(=学期2ヶ月目の中旬~下旬)
・試験時間 1時間~2時間
・出題範囲 1~3章+Labで学んだ内容
・出題形式 Multiple choice questions(MCQ)又は短文回答式。プログラミングの授業は課題が2~3つ与えられ、実際にコードを書くスタイル。
出題範囲は小テストと変わらないことも多かったのですが、大きな違いは短文回答式の問題が出されること。
短文回答式の問題には自分の言葉で回答しなくてはなりません。
また、問題数も増えます。よってその分難易度は上がりました。
教科書やウェブサイトの記述の丸暗記をそのまま記載することは、カンニングとみなされます。最悪の場合0点になり、学校にもカンニング者として報告されます。カンニングに対する扱いは日本よりかなり厳しいと感じました。
期末試験について
・時期 8月初旬~中旬(=学期4ヶ月目の初旬~中旬)
・試験時間 2時間~3時間
・出題範囲 1~3章+Labで学んだ内容 or 1学期に学んだ内容全て(科目による)
・出題形式 短文/長文回答式がメイン。プログラミングの授業は課題が2~3つ与えられ、実際にコードを書くスタイル。
配点と成績
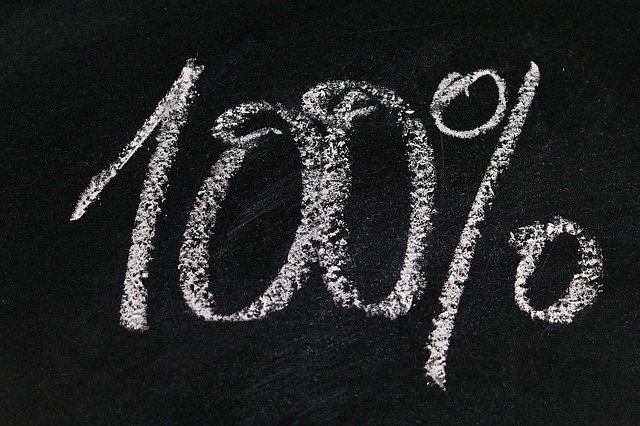
配点は科目によって若干異なるのでイメージとして割合を載せます。
課題(20%)、小テスト(20%)、中間試験(30%)、期末試験(30%)
上記の総合点で100%(=100点満点)となります。
また、総合点で50%以上+テスト部分(小テスト+中間+期末)で最低限50%の成績を取れていなければ
科目を修了(Pass)できないというルールもあります。
よって、いくら課題で点数を稼ごうと、テストの出来が悪ければ修了できない可能性もあります。

さらに、仮に修了できたとしても、一定の成績が取れていない場合、次学期に受講しなければいけない必修科目を受講できない場合があります。
筆者は1科目このパターンに陥りました。
この場合は、再度お金を払って同じ科目を受講しなおし、成績要件を満たさなくてはいけません。
(1科目=650ドルだったので、6万円近く損することになりました・・・。)
※カレッジによってルールや修了要件は異なりますが、恐らくどのカレッジも成績に関しては厳しいはずです。
補足

オンラインでの試験実施に関して
オンラインならではのルール等をまとめます。
まず前提として、試験進行の細かいルールは、各教員の裁量にゆだねられていました。
なので、まじめな先生は厳しくチェックしていましたし、適当な先生は途中でログアウトしていました・・・。笑
・試験中はカメラとマイクON:不正防止のためです。ただ、マイクに向かって暴言を吐く学生がいたので(問題が難しすぎてキレていた?)、途中からマイクはOFFでもよくなりました。笑
・試験時間はシステムで管理されているためごまかせない:Web上の試験システムにログインし、試験開始ボタンをクリックすると、自動的にカウントダウンタイマーがスタートする方式でした。
心臓に悪くて私は嫌いでした←
・学生証やパスポートチェックが入る科目もあった:試験前に一人一人、Zoomのブレイクアウトルームに呼び出されてIDチェックを受けました。なりすまし防止ですね。何も悪いことをしていないのにちょっと怖かったです。
・管理が適当な科目もあった
前述のとおり。通常は教授もビデオ会議システムにログインして不正を見張っているのですが、某授業では教授が「Good luck!」と言ったのを最後に消えるという珍事件がありました。
・一度回答すると戻れない場合も
基本的に、どの試験も1問回答するごとに回答を保存(=Saveボタンを押す)して次の問題に進みます。
ですが、教授の設定により、一度保存するともうその問題には戻れないというパターンの試験もありました。
要は、それがファイナルアンサーとなり、回答の見直しや修正ができないのです。
対面の試験ではまずありえないことだと思うのですが、これは地味に辛かったです。
厳しくない教授だと、前の回答に戻れるように設定しておいてくれたのですが。。。
課題について
試験以外に、課題があります。
課題は、レポート、プレゼンテーション、プログラミングと、多種多様。
課題が出る時期や締め切りも科目によりバラバラ。
私の場合、毎週課題がある科目が2科目、数週間に1回課題がある科目が2科目でした。
よって毎週何らかの課題締め切りorテスト勉強に追われている感覚だったので、
休む暇はないに等しいです。
全体を振り返って

最初は少し余裕を見せていた愚かな私でしたが、そんな幸せな時期は開始数週間程度で終わりました。
結果的に、公立カレッジでの勉強は想像以上に大変でした。
本来は英語で学ぶのが理想的なのかもしれませんが、英語力の不足などで理解が追い付かないのであれば、
ガンガン日本語の教材も活用して専門知識の強化を図ると効率的で良いと思います。
私は、IELTSのリーディングスコア7.0、リスニングスコア7.5でしたが、
英語力が不足していてついていけないと思うことがあったので
途中から日本語の専門書を買いました。
英語力問題については、授業開始当初に感じていたこと(以下の記事にまとめました)とは若干変わりましたね
ありのままに書きましたが、これからカレッジを志す方の参考になれば幸いです。
MEZ





